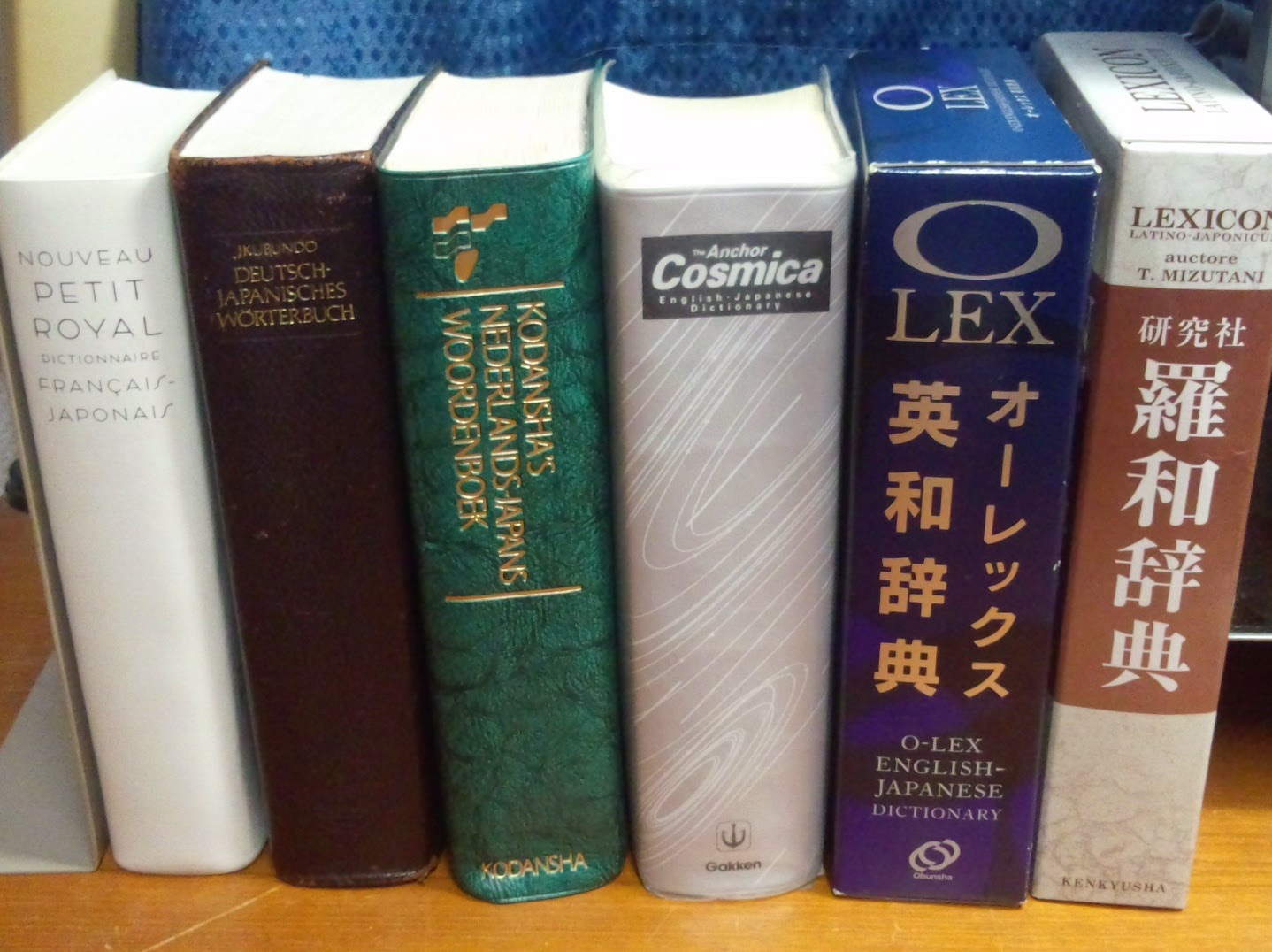|
| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |
マルコによる福音書12・13~27
「さて、人々は、イエスの言葉じりをとらえて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。彼らは来て、イエスに言った。『先生、わたしたちは、あなたが真実な方で、だれをもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは、律法に適っているでしょうか。適っていないでしょうか。納めるべきでしょうか。収めてはならないのでしょうか。』イエスは、彼らの下心を見抜いて言われた。『なぜ、わたしを試そうとするのか。デナリオン銀貨を持って来て見せなさい。』彼らがそれを持って来ると、イエスは、『これは、だれの肖像と銘か』と言われた。彼らが、『皇帝のものです』と言うと、イエスは言われた。『皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。』彼らは、イエスの答えに驚き入った。復活はないと言っているサドカイ派の人々が、イエスのところへ来て尋ねた。『先生、モーセはわたしたちのために書いています。「ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎをもうけねばならない」と。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、跡継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、跡継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして、七人とも跡継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女はだれの妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。』イエスは言われた。『あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、めとることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の「柴」の個所で、神がモーセにどう言われたか、読んだことがないのか。「わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。』」今日もマルコによる福音書を開きました。先週はイースター礼拝でしたので、読む順序を変えて、イエスさまが復活される個所を読みました。結論を先に読んだ形です。しかし、今日から元の順序に戻ります。
今日の個所に出てくるのは、イエスさまの言葉じりをとらえて陥れるために近づいてきた人々です。そのような人々にイエスさまは苦しめられました。この人々がイエスさまのもとに近づいてきたのはイエスさまに救いを求めてきたのではありません。イエスさまを陥れるために来ました。イエスさまがお語りになる言葉の中に矛盾や欠点を探し出して、イエスさまを訴える口実を得るために来ました。
つまり、この人々がイエスさまにしている質問はすべて罠であるということです。そういう意図であるということを、わたしたちはあらかじめ理解しておく必要があります。この人々の言い分を真に受けてはいけません。
イエスさまだけでなく、わたしたちのまわりにも、そういう人たちがいると思います。うんうんと頷きながら話をよく聞いてくれる人だと思って信頼し、心を許していろいろ話すと、それが罠だったという経験を、わたしたちも味わってきたのではないかと思います。本当に心を許せて何でも話せる相手を見つけたいと願っても、なかなか難しいわけです。何度か痛い目に会ってみないと分からないところがあります。
しかし、イエスさまの場合は、わたしたちの場合とは違う面がありました。それではイエスさまにとって、本当に心を許せて何でも話せる相手はだれだったのか、そういう人たちが実際にいたのかということは考えてみる必要がありそうです。
先ほど申し上げたとおり先週はイースター礼拝でしたので、この福音書を読む順序を変えて結論を先に読みました。イエスさまの復活の個所を先に読みました。しかし、その読み方は飛ばし過ぎです。イエスさまの十字架上の死の場面を飛ばしてしまっています。それは、今日の個所と先週の個所の間には、決して飛ばしてはならない、省略してはならない内容があったということです。それがイエスさまの十字架上の死の場面です。
そこに至ってイエスさまは完全に孤独になられました。十字架上にはりつけにされたイエスさまには、心を許して何でも話せる相手というような意味での友達は一人もいませんでした。それどころか、イエスさまのもとに集まっていたすべての人が、その日までイエスさまがお話しになってきたことのすべてを悪く受け取りました。すべての弟子が裏切り、すべての人の心がイエスさまから離れました。しかし、それこそが父なる神の御心であり、イエスさまがお望みになったことでした。イエスさまはすべての人の身代わりに十字架にかけられることを、御自身でお望みになったのです。
弟子たちの中の一人として「イエスさまは悪くありません。イエスさまを十字架につけるのなら、代わりにこの私を十字架につけてください」と申し出る人はいませんでした。それどころか、十二人の弟子の一人のイスカリオテのユダは、自分から祭司長たちのところに出かけて行き、お金でイエスさまを売り渡す約束を取り交わしてきました。一番弟子のペトロさえ、鶏が二度泣く前にイエスさまのことを三度知らないと言いました。それらのこともすべて、イエスさま御自身が初めからご存じであり、御自身がお望みになったことです。イエスさまは弟子たちの身代わりに十字架にかけられることを、御自身でお望みになったのです。
その意味では、イエスさまは今日の個所に出てくるような、言葉じりをとらえて陥れる人々がいることは初めから分かっておられましたし、そういう人々がいるからと言って、言い方を変えたり内容を変えたりすることはなさらなかったと言えます。もちろんその人々が仕掛けてくる罠に対する警戒心はお持ちでした。しかしそれは、イエスさまが逃げ腰であられたというような意味ではありません。
イエスさまのお心をどのように表現すればよいのかは、迷うところです。いろいろ考えさせられました。それで思いついたことを言わせていただけば、その人々が仕掛ける罠にイエスさまが陥らないようにすることは、イエスさまにとっては、その人々にそれ以上に罪を犯させないようにすることを意味していたのではないだろうか、ということです。
なぜなら、人に罠をかけて陥れること自体が罪なのですから。罠に陥った人の側も悪い、不注意の罪を犯しているというように言うのはひどいことです。間違っています。それは、泥棒に遭った人を「あなたも不注意だったから悪い」と責めるのと同じです。それはひどい言い方です。しかし、イエスさまは、イエスさまを罠にかけて訴える口実を探して殺してしまおうとしている人々にもこれ以上の罪を犯してほしくないと願っておられたのです。だからイエスさまは彼らの仕掛けた罠に陥らないように注意深く対処されたのです。イエスさまが逃げ腰だったということではありません。
今日の個所に出てくる、イエスさまに仕掛けられた罠は二つです。一つは、ユダヤ人がローマ皇帝に税金を納めることは律法に反していることかどうかという質問です。もう一つは復活の問題でした。
税金の問題について、「ユダヤ人」とは記されていませんが、それ以外の意味はありません。ユダヤがローマ帝国に支配され、属国になっていた時代の話です。ユダヤ人、なかでもファリサイ派の人々は、ユダヤのナショナリストのような存在でしたので、ユダヤがローマの属国であることが不愉快でたまりません。早く自立したいと願っていました。だからとくにファリサイ派の人々はローマ皇帝に税金など納めたくありません。国民感情としてもローマ皇帝に税金など納めたくないと思っている人は大勢いました。
そのような状態の中で、もしイエスさまがローマ皇帝に税金を納めることは律法に反しているので、納めてはならないとお答えになれば、多くの人から支持され、賞賛された可能性があります。そのことを主張して選挙に出れば多くの票を集めることができたかもしれないほどです。しかし、そのように国民に対して呼びかけることは、ローマ皇帝とその支配下のユダヤ国王に対する反逆を意味するわけですから、その場で即、イエスさまを反逆罪の現行犯で逮捕できたわけです。
しかも、それはもう少し複雑な事情がありました。当時のローマ皇帝は自分は「神」であると称していました。ローマ皇帝が神であることを主張する字が、皇帝の肖像と共に、当時の貨幣に書かれていました。それは確実に律法に反します。「わたしのほか何ものをも神としてはならない」にも「自分のために刻んだ像を作ってはならない」にも反します。そのため、ユダヤ人にとってのローマ税問題は政治的・経済的な問題であるだけでなく、宗教的・信仰的な大問題だったのです。
しかし、イエスさまのお答えは、驚くべきものでした。銀貨をもって来させ、「これはだれの肖像か」とお尋ねになり、「皇帝のものです」と彼らが答えると、「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい」と言われました。まさか冗談でおっしゃったわけではないと思いますが、顔と名前が書いてあるものをその顔と名前の人に返しなさいとおっしゃったわけです。
そのお答えはローマ皇帝に税金を納めることを肯定する意味を持ちます。しかし、「神のものは神に返しなさい」とおっしゃいました。「皇帝」と「神」を区別されました。ローマ皇帝に税金を納めることは、真の神を冒涜することにはならない。神は神だ。皇帝は神ではない。そのことをはっきりおっしゃっているのです。
もう一つの罠は復活の問題でした。復活を否定したくて否定したくてたまらない人たちがいました。サドカイ派です。だから彼らがイエスさまに質問をしているのは、復活を信じることがいかに矛盾に満ちていて滑稽であるかを言いたがっているだけです。イエスさまが矛盾したことを言おうものなら、そこに噛み付いてやれと、構えているだけです。
それで彼らが持ち出したのが、レビラート婚と呼ばれる当時のルールでした。その内容は「ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎをもうけねばならない」というものです。ところが、その妻が七人の兄弟全員と結婚したが、子どもをもうけることができませんでした。その妻が復活したときに、誰の妻になるのでしょうかという質問です。
この質問も真に受けてはいけません。この質問から感じられるのは真面目さのかけらもない人たちだということです。にやにや笑っているような顔を想像できます。そもそもこういうことを持ち出すこと自体が不愉快です。結婚や出産、あるいは離婚。その他いろいろな複雑な人間模様。このようなことで苦労したことがあるような人は、このようなことをたとえ話として持ち出したりはしません。
「あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか」。
イエスさまが問うておられるのは、信仰です。あなたがたには信仰があるのかと問うておられるのだと思います。自分が信じられないことがあると、ごちゃごちゃと屁理屈をこねて言い逃れしようとしている人たちに、イエスさまは憤っておられます。
(2015年4月12日、松戸小金原教会主日礼拝)