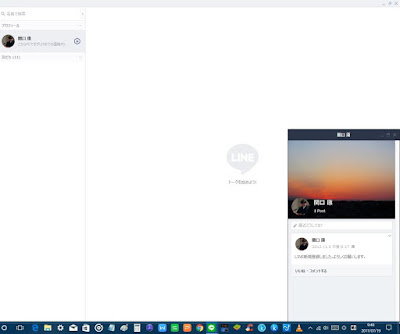|
| 日本キリスト教団上総大原教会(千葉県いすみ市大原9696) |
ローマの信徒への手紙13章8~10節
関口 康(日本キリスト教団教師)
「互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしているのです。『姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな』。そのほかどんな掟があっても、『隣人を自分のように愛しなさい』という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法を全うするものです。」
上総大原教会の皆さま、おはようございます。日本キリスト教団教師の関口康です。この教会で3回目の説教をさせていただきます。今日もどうかよろしくお願いいたします。
3回目のご依頼をいただいてすぐ、どんな話をさせていただこうかと考えました。1回目は1月1日の新年礼拝、2回目は4月2日でした。2回とも「伝道」の話をしました。
それで結局、今日も「伝道」の話をします。しかし、いわゆるハウツーの話ではありません。そういう話が私にできないわけではありません。むしろいくらでもできます。
しかし、はっきり言わせていただきますが、ハウツーの話というのはこの教会の状況にそぐいません。現実味が全くありません。お題目のような話であれば、目をつぶったままでも言えます。こんな感じでしょうか。
とにかく人を誘わなくては教会に誰もいなくなるので、人を教会に誘いましょう。まず家族に伝道しましょう、次は友人に伝道しましょう。ご近所の人を教会に誘いましょう。
言葉で伝えるのが難しいようなら、チラシを配りましょう。トラクトというのがキリスト教書店に売っているので、そういうのを買って配りましょう。いろいろ有名人に来てもらって講演会やコンサートを開きましょう。
いろいろやってみました。結局教会に人は集まりませんでした。そうか、いろいろやってもダメなのだ。日曜日の礼拝が教会のすべてなのだ。とにかく大事なのは礼拝なのだ。
聖歌隊が欲しいが、人がいないからうちでは無理だ。奏楽者がいて欲しいが、自動演奏機でもやむをえない。とにかく礼拝は説教を聴くことだ。神の言葉を聴くことだ。
そこまで追い詰められて、思い詰めて、とにかく礼拝を重んじることにした。説教を重んじることにした。ところが、その説教がいつもつまらない。私の心に届かない。礼拝しかない教会で、説教しかない礼拝で、説教がつまらないとなると、この教会どうなるの。
よし分かった。私が牧師になってやろう。私が説教してやろう。そうすれば、この教会は以前の活気を取り戻すことができるだろう。などなど。こんなふうに、わたしたちは考え続けていくわけです。
そんなことまで考えている人はいないなどと、どうか思わないでほしいです。教会に来ている人たちはみんな、大なり小なり、こういうことを真剣に考えています。
そして私は今日このことを皆さんにはっきり申し上げておきたいのですが、教会のことを心配しているのは教会に来ている人たちだけではありません。教会に来ていない人たちも教会のことを真剣に考えてくださっています。教会の門を一度もくぐったことがない人たちも同じです。
昨年度私が勤務した学校でのことです。生徒たちにとって例外なく興味があったのは「教会は儲かるのか」ということでした。「牧師はどれくらい給料をもらえるのか」ということでした。
そういうことを、授業中でも、廊下を歩いているときでも、繰り返し質問されました。そんなに興味あるならと、私が担当していたすべてのクラスで「教会の経済と牧師の生活」というテーマで黒板に図解しながら解説したくらいです。
「へえ、たいへんなのですね、それではとても生活できないではありませんか」と心配してくれた生徒もいました。「ええっ、教会の献金はかわいそうな子どもたちや貧しい国の人々に送られているのではなかったのですか」と悲しそうな顔をする生徒もいました。
あるいは、宗教団体というのはとかくお金に汚い人たちの集まりだと教えられてきたのかどうかは分かりませんが、「教会の経済と牧師の生活」についての図解付きの私の説明を聞いて、「なんだ、意外に普通のようだ。つまらない」という反応をした生徒もいました。お金の話をすれば私の鼻を明かせると思ったのかもしれません。
いまお話ししているのは、教会の運営や経済について心配しているのは教会員だけではないということです。多くの人たちが、そして高校生たちも、心配してくれています。
「そういうのはただの興味本位である」と言ってしまえば、それまでです。しかし、わたしたちが見逃してはならないのは、教会の存在は多くの人々から関心を持たれているということです。教会は社会の中で全く孤立しているわけではないということです。
そして、その教会に対する人々の関心は、必ずしも批判的な視線ではありません。好意的な視線を多く含んでいます。
なぜ今私はこんな話をしているのかというと、わたしたちが教会の存在をこの社会の中でとにかく必死で守り抜いていかなければならないと思っているときに、つい自分たちのことを社会の中で完全に孤立し、非難を受け、中傷誹謗にさらされているかのように感じてしまうことがあるからです。しかし、そんなふうに考える必要はないと言いたいのです。
そろそろ今日の聖書の箇所のお話をしなければならないと思っています。しかしここまで話してきたことは今日の聖書の箇所とは無関係なおしゃべりではありません。ものすごく関係していることだと思っているので、このような話をしています。
「互いに愛し合うことのほかに、だれに対しても借りがあってはなりません」(8節)と書いてあります。これは裏返していえば「互いに愛し合うことに限っては借りがあっても構いません」ということになります。論理的に考えれば、そういうことになります。
しかし「借りがある愛」とは何のことでしょうか。「愛を貸してもらう」はどういうことでしょう。「愛を返す」という話であれば、少しは理解可能になるかもしれません。
これは愛の話です。最初は「アイ・ラブ・ユー」から始まります。そうでない始まり方はありえません。しかし、その最初のプロポーズは、必ずどちらか一方が先に言うと思います。必ずそうなります。例外はありません。事前の打ち合わせでもあれば別ですが、それもなしに互いに同時に「アイ・ラブ・ユー」を言って同時に相互の愛が始まったという人は、通常いません。
そしてそこから先は危険な状態です。もしかしたらそのプロポーズを相手に断られるかもしれないからです。その「アイ・ラブ・ユー」のボールは、ピッチャーの手からとにかく離れました。しかし、それをバッターが打たないかもしれません。キャッチャーが捕らないかもしれません。デッドボールになるかもしれません。バックネットにダイレクトで突き刺さるかもしれません。
しかしその「アイ・ラブ・ユー」ボールをホームランにするバッターもいます。サヨナラホームランでさようならという寂しい話ではありません。ピッチャーの全力投球を全力で打ち返したバッターは真剣なプロポーズに誠実に応えたのです。「私はあなたを愛している」と言われて「私もあなたを愛している」と愛し返したという意味です。ということにしておきます。
今申し上げているのは「借りのある愛」とは何なのかについての説明です。はっきりしているのは、愛は必ずどちらかから一方から始まるものだということです。必ず片想いから始まります。例外はありません。それを別の言い方でいえば、愛が貸し借りの関係にあったということです。先に愛されて、その愛を返すということですから。
しかし、ここでパウロが言おうとしていることの中心が「愛に限っては借りがあっても構いません」ということかどうかについては、疑問があるかもしれません。そうではない。パウロが言おうとしているのは「貸し借り」があってはいけないという、ただそれだけであるという見方は出てくるかもしれません。
しかし、その問題については、前後の文脈との関係を考える必要があります。「愛」の話は12章9節から始まっています。13章10節まで「愛」の話が続いています。これで分かるのは、今日の箇所でパウロが「愛」について語っていることは間違いないということです。
それはつまり、パウロがしているのは、人間関係の中には貸し借りがあってはならないという話「ではなく」愛には貸し借りがあってもよいという話「である」ということです。
ここでもう一つ、今日の箇所で大事なことをお話しします。それは「人を愛する者は、律法を全うしているのです」という言葉に続く部分に関することです。
「『姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな』、そのほかどんな掟があっても、『隣人を自分のように愛しなさい』という言葉に要約されます」(8~9節)とあります。
これについて簡単に説明しますと、モーセの十戒の前半の4つの戒めは「対神関係」(神との関係)についての戒めであり、後半の6つの戒めは「対人関係」(人との関係)についての戒めであると整理できます。
そしてパウロが言っているのは、そのモーセの十戒の後半の「人との関係」についての戒めの部分を要約すると「隣人を自分のように愛しなさい」(レビ記19章18節、マタイによる福音素19章19節)という一言でまとめることができるということです。Love your neighbor as yourselfです。これを校訓にしているキリスト教学校があります。
そして「愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法を全うするものです」(10節)と書かれています。ここに至ってわたしたちが考えなければならないのは、「隣人とは誰のことか」という問いです。それは、あの「善きサマリア人のたとえ」(ルカによる福音書10章25節以下)でイエスさまが発せられたのと同じ「隣人とは誰のことか」という問いです。
この問いの答えははっきりしています。「隣人」とは教会の人々だけではありません。キリスト者だけではありません。教会の「内」にいるか「外」にいるかの区別がない「すべての人」を指しています。それが「隣人を自分のように愛しなさい」という戒めの「隣人」の意味です。
そのことが、今日最初のほうでお話しした「教会に関心を持っている人々が教会の外にも大勢いる」という話に関係してきます。また、次にお話しした「貸し借りのある愛」の話につながってきます。
今のわたしたちは、教会が無くならないように、教会の存在を守り抜くことでとにかく必死です。しかし祈っても願っても、教会にはなかなか人が来てくれません。そのようなときに、わたしたちがもしかしたら陥るかもしれないのは、教会の周りにいるのは敵だらけだ、という感覚です。
孤立感がきわまり、深刻な疑心暗鬼の状態に陥ってくると、そういう感覚が去来します。そして、それが「敵」であるならば、その存在がだんだん憎らしく思えてきます。愛することなどとんでもないという感情が生まれてきます。
しかし、それではだめです。教会の外にいる人々を心から愛することなしに、伝道は成立しません。「隣人」はキリスト者だけではありません、教会員だけではありません。教会に来てくれない、洗礼を受けてくれない、神にも聖書にもキリスト教にも興味を持ってくれない方々が「隣人」です。
その人々をわたしたちが愛することが、神から求められています。それができないと伝道はできません。わたしたちが世界を敵視しているかぎり、教会は孤立の一途です。もしそのような感覚にわたしたちが少しでも陥っているなら、根本的な方向転換が必要です。
「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された」(ヨハネによる福音書3章16節)と書かれているではありませんか。神が愛された「世」は、世界の「世」、世間の「世」です。字が同じであるだけでなく、意味も同じです。「神は世界を愛された」のです。「神は世間を愛された」のです。
この意味での「世」も、すでに神を愛し返した人々ではなく、むしろ、そうではない「すべての人」を指しています。
神が世間を「その独り子をお与えになったほどに」愛しておられるなら、わたしたちも世間を心から愛するべきです。そうでなければ「伝道」というものは成り立ちません。
この件についてみなさんによく分かっていただけそうな「たとえ」が見つかりました。
わたしたちが教会の中から窓の外を指さしながら「こんな人たちに負けるわけにはいかない!」などと言っているような教会に、だれが行こうと思うでしょうか。
この問題をよく考えていただけば、教会の進むべき道が見えてくると思います。
(2017年7月16日、日本キリスト教団上総大原教会 主日礼拝)