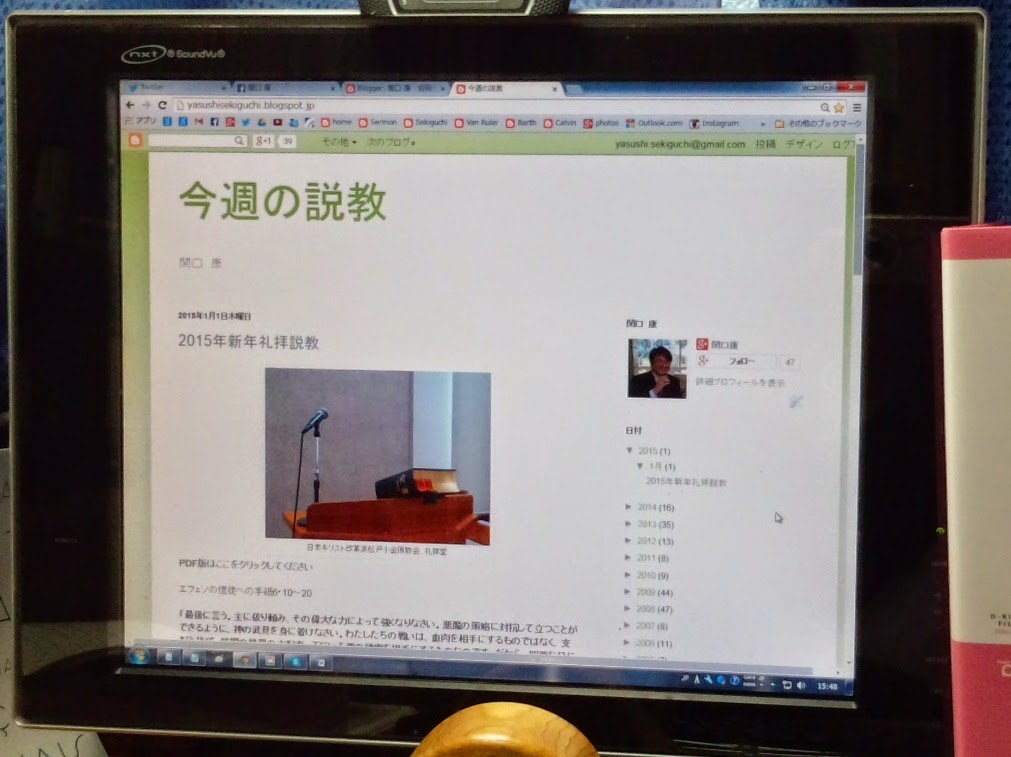|
| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |
PDF版はここをクリックしてくださいマルコによる福音書7・1~23
「ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちが、エルサレムから来て、イエスのもとに集まった。そして、イエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。――ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また、市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない。そのほか、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。――そこで、ファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。『なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。』イエスは言われた。『イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。「この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。」あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。』更に、イエスは言われた。『あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは、「父と母を敬え」と言い、「父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである」とも言っている。それなのに、あなたたちは言っている。「もし、だれかが父または母に対して、『あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です』と言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだ」と。こうして、あなたたちは、受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。また、これと同じようなことをたくさん行っている。』それから、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。『皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。』イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこのたとえについて尋ねた。イエスは言われた。『あなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか。すべて外から体の中に入るものは、人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうして、すべての食べ物は清められる。』更に、次のように言われた。『人から出て来るものこそ、人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出て来るからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、好色、ねたみ、悪口、傲慢、無分別など、これらの悪はみな中から出て来て、人を汚すのである。』」今日は今年最後の主日礼拝です。引き続きマルコによる福音書を開いていただきました。この個所に登場するのは、イエスさまと弟子たち、そしてイエスさまと弟子たちのことを快く思っていない人々です。その人々とイエスさまが論争する場面です。
その人々がイエスさまに言いました。「なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか」。イエスさまの弟子たちの中に食事の前に手を洗わない人がいたようです。それを見た人々がイエスさまにクレームをつけました。衛生上の問題としてではありません。彼らは、食事の前に念入りに手を洗わなければならないという古くからの言い伝えを固く守ってきた人々でした。その言い伝えをイエスさまの弟子たちが守っていないということを問題にしたのです。
なぜそういうことが言い伝えられていたのかは、ここには書かれていませんし、よく分かりませんが、おそらく当時のユダヤ社会の常識のようなこととして考えられていたのではないかと思います。常識を破ることが非常識です。イエスさまの弟子たちは非常識呼ばわりされたのです。
その人々が守ってきた言い伝えはそれだけではありませんでした。「市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない」と記されています。市場に買い物に行った人は、帰ってすぐには食事ができなかったようです。身を清める必要がありました。市場は汚れた場所であるとみなされていたのです。しかし、これも衛生上の理由ではありません。彼らはファリサイ派の人々であり、律法学者です。彼らが問題にしたのは宗教的な理由です。食事の前に手を洗わなければならないことも、市場から帰ってくると身を清めなければならないことも、彼らの宗教的確信に基づく考えでした。
しかしイエスさまはその人々に反論されました。その人々をイエスさまは「偽善者」であると非常に強い言葉で非難されました。「イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。『この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。』あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている」。
もちろんイエスさまは、このようにおっしゃることで、弟子たちのことをかばわれたのです。食事の前に手を洗うことが悪いということではありません。しかし、手を洗わないような人は食事をしてはいけないというほどではないとイエスさまはお考えになりました。ある意味で個人の自由の領域のことであるとみなされました。その自由を奪う形で「○○しなければならない」と決めつけること、○○しない人は食事をしてはならないと排除することを、イエスさまはお嫌いになったのです。
しかもイエスさまは、そのようなクレームをつけてくる人々を「偽善者」とお呼びになって、対決姿勢をとられました。なぜそこまでの強い態度をとられたのでしょうか。食事の前に手を洗うことも、市場から帰ってくると身を清めることも、聖書そのものの教えではなく、人間の言い伝えにすぎないものだとおっしゃりたかったからです。
その人々が問題にしたことの理由はこの個所には必ずしも明確に書かれていません。しかし、それが宗教的な理由であるとすれば、ある程度までなら想像がつきます。
手を洗うことと身を清めることとに共通している要素は、日々の食事に象徴されるふだんの生活、あるいは市場に象徴される世間の営みは汚れているという物の見方です。そういうものに近づいたり触れたりすることで人は宗教的な意味で汚れると彼らは考えたのです。だから、家に帰れば身を清めなければならない、食事の前には念入りに手を洗わなければならないという話になったのです。
しかし、イエスさまは、そのようなことは全くお考えになりませんでした。彼らの考え方はイエスさまのお考えの正反対でした。もしイエスさまが彼らと同じような考えをもっておられたとしたら、伝道は成り立ちませんでした。
汚れた霊にとりつかれた人に対し、重い皮膚病の人に対して、イエスさまがなさったことは、御自身の手でその人々の体に直接触れることでした。
見ず知らずの大勢の群衆が押し寄せてきたとき、その人々は汚れているというようなお考えをイエスさまがもしお持ちになっていたら、その場にとどまって伝道されるどころか、群衆に背を向けて逃げ出されたことでしょう。しかし、そのようなことをイエスさまはなさいませんでした。
御自身のもとに集まって来た五千人の人々に五つのパンと二匹の魚を取り分けられたときも、「まずよく手を洗ってから食べてください」ということをおっしゃいませんでした。
安息日にイエスさまの弟子たちが麦畑を通るとき、麦の穂を摘んで食べ始めたとき、「手を洗わなければ食べてはならない」とはおっしゃいませんでした。
衛生上の観点からいえば別の言い方をしなければならないのかもしれません。しかし、イエスさまにとって、食事をすることと手を洗うこととは、何がなんでも結びつけて考えなければならないほどのことではなかったのです。
そして、イエスさまにとってそれ以上に問題だったのは、我々の日常生活そのものや世間そのものを汚れたものであるとみなす、ファリサイ派の人々や律法学者の思想そのものです。「人を見れば泥棒と思え」という言葉がありますが、人を見れば不潔と思う。世間は不潔だと思う。わたしたちまでがそのような感覚を持ち始めたら危険信号です。人に近づけなくなります。
しかし、それだけならまだいいほうです。イエスさまが彼らを「偽善者」とお呼びになったのは、自分たちは汚れていないと思い込んでいる人々だったからです。世間は汚れているが、我々は汚れていない。世間の汚れがとりついたら、さっさと水で洗えば、自分たちの清さは取り戻される。本当にそうだろうかと、イエスさまはおっしゃりたかったのです。汚れの度合いは大差ないのではないか。水で洗っても落ちない汚れがあなたがたの心の中にあるのではないか、と。
今申し上げたことに関係することが次の段落に出てきます。ここでイエスさまが指摘しておられるのは律法学者の偽善性です。一方で彼らはモーセの十戒に基づいて「あなたの父母を敬え」と教えている。しかし、他方で彼らは人々にあなたの父または母に「あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です」といえば父母を扶養する義務が免除されると教えていたというのです。
この件は教会も気をつけなければなりません。「教会に献金します」「教会の奉仕です」といえば、家族に対する義務が免除されるわけではありません。イエスさまはそのような態度こそが偽善であると激しくお嫌いになりました。家族や家庭を大切にすることと神への熱心な奉仕とは両立させなければなりません。どちらか一方を重んじるゆえに他方を軽んじるという態度そのものが、イエスさまにとっては問題だったのです。
14節以下の段落に記されているのは、イエスさまの基本的なお考えです。「皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである」。これが何の話なのかを弟子たちは理解できませんでした。それであなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか」とイエスさまに呆れられました。
皆さんはお分かりでしょうか。これはトイレの話です。今年最後の礼拝でトイレの話をすることになるとは思いませんでした。イエスさまが「わたしの言うことを聞いて悟りなさい」とおっしゃっているのは言葉を濁しておられるのです。私も詳しい説明は省略します。食べたものが外に出る。出て来たものには不潔な面がある。しかし、食べものを食べること自体で人を汚すことはないということをイエスさまはおっしゃっています。
しかし、これはもちろんたとえ話です。イエスさまがおっしゃりたいことは、「人から出て来るもの」の問題です。人の心の中にあるものの汚れの問題です。わたしたちの心の中にもある罪の問題です。手を洗うことも身を清めることも大事です。しかし、それよりももっと大事なことは、私たちの心が清くなることです。心の中から出て来るものが人を汚すのです。毒舌の持ち主は気をつけましょう。私も気をつけます。
(2014年12月28日、松戸小金原教会主日礼拝)