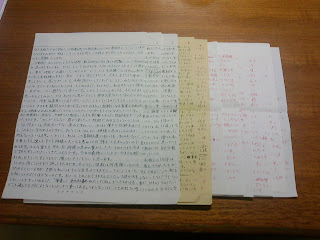ぼくの書斎の本棚から、とんでもないものが発掘されました。
生まれて初めての「夏期伝道実習」のときの説教原稿(手書き)です。当時、東京神学大学3年生。
ぼくはちょうどハタチ。今から26年前、1986年(昭和61年)8月24日、日本基督教団宍喰教会の主日礼拝でおこなった説教です。
その教会は、徳島県の最南端に位置する宍喰町(現在「徳島県海陽町」)にあります。
ワープロもパソコンも高根の花だった時代の手書き原稿でした。牧師になってからも高知県高知市を皮切りに、高知県南国市、福岡県北九州市、兵庫県神戸市、山梨県甲府市、山梨県中巨摩郡敷島町(現在「甲斐市」)、そして現在の千葉県松戸市と、転居を繰り返しましたので、どさくさの中で、こんな原稿はとっくの昔に失われていると思っていました。
このたびブログ公開する理由は、自分の過去の説教(しかも神学生時代の説教)を「良い」と思っているからではありません。いくらなんでも、それだけは無いです。ありえない。
そういう自画自賛のたぐいとはちょうど正反対の理由です。このような説教は、今のぼくなら決してしません。それだけは断言できます。強い自戒と反省をこめての公開です。
(1)今なら決して用いない語や言い回しが繰り返し出てきます。
(2)一回の説教としてはあまりにも長大で饒舌すぎます(今の約二倍です)。
(3)比喩が幼稚すぎます。テレビやマンガを見すぎです。
(4)誤字もそのまま転記しておきました。
改めて読み直してみて、うわあ、こんなにひどかったのかと、恥ずかしすぎて、顔から火が噴き出ました。この翌年、加藤常昭教授から「キミの説教は下品だね」と言われたことの意味が今さらながらよく分かりました。
しかし、過去の恥を自分でさらすのは、人にさらされるよりは、気楽なことです。過去のぼくもぼくであることには違いないので、なかったことにすることはできません。責任はあります。
そして、夏期伝道実習そのものは、とても楽しい思い出でした。宍喰教会の皆さまに大変お世話になりました。本当にありがとうございました!
------------------------------------------------
東京神学大学夏期伝道実習説教
(1986年8月24日、日本基督教団宍喰教会主日礼拝)
「取税人ザアカイ」
ルカによる福音書19・1~10
関口 康
「さて、イエスはエリコにはいって、その町をお通りになった。ところが、そこにザアカイという名の人がいた。この人は取税人のかしらで、金持であった。彼は、イエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので、群衆にさえぎられて見ることができなかった。それでイエスを見るために、前の方に走って行って、いちじく桑の木に登った。そこを通られるところだったからである。イエスは、その場所にこられたとき、主を見上げて言われた。『ザアカイよ、急いで下りてきなさい。きょう、あなたの家に泊まることにしているから』。そこでザアカイは急いでおりてきて、よろこんでイエスを迎え入れた。人々はみな、これを見てつぶやき、『彼は罪人の家にはいって客となった』と言った。ザアカイは立って主に言った。『主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍にして返します』。イエスは彼に言われた。『きょう、救がこの家にきた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子がきたのは、失われたものを尋ね出して救うためである』」(口語訳)。私が生まれてはじめて訪れたこの宍喰の町での教会奉仕も今日が最終日ということになりました。みなさまのお祈りと励ましによって44日間という日程を全うすることができましたことを心より感謝いたします。
この教会に与えられている大きな使命、数え切れないほど多くの問題について、今ひとたび思いかえすのですが、やはりどうして私のような大任にふさわしからざる小さく愚かしい者を神様がお遣わしになられたのかということは、不思議でなりません。
私のような人生経験のまずしい者が、今まで学んできたこと、今まで生きてきた歩み、考えてきたこと、感じてきたことを全部語りつくしてしまったところで、みなさんにとってはすでによく知っておられることでありまして、わざわざ私の口からして語るに及ばないことに過ぎないと思うのです。
しかし、そうはいいましても、またよくよく思いかえしてみるに、では私のようなものがどうして神学大学などで学んでいるのだろうか、将来伝道者として立たせていただこうとしているのだろうか、ということになると、ますます疑問なのであります。何かおまえに牧師になる資質でもあったから、神様はおまえを選んだとでもいうのか。いや全くそうではなかったのです。
ある世界的に有名な、今日のキリスト教会に大きな影響を与えた牧師先生がこう言ったそうです。「わしがどんなに罪が深くたって、牧師でおれるなどということは、こりゃ何としても合点のいかない恵みですわい」。偉大な牧師先生でさえこのように言われるのですから、私などはほんとに神様の恵みによるほか何もないといえます。
だからして、私はこの夏期伝道においても、私のようなバカ者でさえ選んで下さる神様の大いなる恵み以外語ることを知らないのであります。どんな者をも包みこむ神様の恵みの豊かさ、ただそれだけを今まで語らせていただいてきたつもりです。今日は最後ということで、今までの総まとめ、おさらいをするつもりで聞いていただきたいと思います。
とにかく同じことばかり語ってきたのです。すばらしい説教は何度聞いても心をうたれる、といいますが、未熟な私にはそんな芸当はできません。ただ1つのことを知っていただくほかないのです。私にはそれしかできませんでした。
友達がおもしろいことを言ってくれました。「聖書って金太郎あめみたいだね。どこで切っても、どこを読んでも同じようなことばっかり書いてある。つまらないけど、でもおもしろいね」。私の説教も、きっと金太郎あめみたいだったでしょう。でも、もしそれが聖書的だったとしたら光栄です。これからも金太郎あめのように生きていかれたらと思います。
今日共に開いた聖書の箇所も、結論は、いつもどおり「神、罪人を救いたもう」であります。大変有名な「取税人ザアカイ」の物語であります。教会学校や保育所の子供たちもよく知っているザアカイさんのお話です。わたしたちも今ひとたび、幼子のようになって、神様の救いの恵みについて学びたいと思います。
取税人とは、ローマのためにユダヤの人々から税金をとりたてる人です。ユダヤの人たちから大変きらわれていました。私たちでも税務所ときくと、どうも苦手であるように思います。あまり裕福でない人にとっては税務所が悪魔のように見えたりします。社会のため、国のため、よいことのためと言われても、やはりあまりイイ気がしません。
しかし、このイエス様の時代の人たちがザアカイたち取税人を見るときの感情は、私たちの税務所に対するものと、ちょっと違う性質をもっていました。それというのも、その時代、ユダヤはローマの属州でありました。ユダヤの人たちはローマ帝国の支配下にあって、大変苦しい、辛い目にあっていました。亡国のうき目にあって精神的にも肉体的にも絶望のどん底にありました。その中にあってザアカイたち取税人は、ローマ帝国のために納める税金を、その苦しんでいたユダヤ人たちから取りたてて、ついでにその手数料を高くとって、それで生活している人たちだったのです。
それも、ザアカイは正真正銘、きっすいのユダヤ人でありました。ザアカイという名前は、純粋なイスラエルの名前で、意味も「純粋」というのですから、純くんだか、純一郎くんだか、そのようなものでした。それにもかかわらず、苦しんでいる貧しいユダヤ人を裏切るかのようにして、うらめしい手数料によって富めるユダヤ人であったのです。ローマ帝国に対するユダヤ人のうらみつらみが、最も極度の形で、彼ら取税人に向かっていくのは当然のなりゆきともいえるでしょう。
特にザアカイ、純一郎くんは、取税人のかしらでありました。もっとも財力のある、もっとも大金持ちの、それゆえ、最もうらめしい対象であったわけです。「われわれは苦しんでいる。けれどもユダヤ人であること、神様がわれわれを選んでくださった約束をひとときも忘れたことはない。だけど、あの取税人ザアカイの野郎は何だ。あいつは売国奴だ、裏切り者だ、ひきょう者だ」と思われていたにちがいないのです。
ローマの属州となってしまっている以上、税金をとり上げられることはさけることができませんでした。ユダヤ人たちが何と考えようと、現実はそうでした。
そして、その税金を集める役をだれかがしなければならなかったのです。憎まれ役を誰かが引き受けなければならなかったのです。ユダヤ人としての誇りをもっている人なら、最初からそのような憎まれることがわかり切っているような役を好んでひきうけたはずはないのです。最初からしたくてしたくてたまらなかったわけではないのです。イヤイヤながらはじめたのです。自分をこのような目にあわせたローマ帝国をうらみつつ、ユダヤ人には申しわけないと思いつつ、小さくなりながらはじめたのです。
しかしながら、人間の成金根性といいましょうか、お金の誘惑に対する弱さといいましょうか、次第に自分の立場に誇りをもちはじめ、ほんとにきらわれようが、1人ぼっちになろうが、村八分にされようが、しかたないほどの取り立てをはじめてしまったのです。
いったん信用をうしなったらそれをとりもどすまで最低10年はかかるといわれています。しかしそれも、努力してとりもどそうとしたらの話です。ザアカイの場合、裏切り者として見離され、なお続けて税金のとりたてをしているのですから、2度と見直されることはないことは確実だったのです。そして、それが確実になった以上、共同体から離れて1人で生きていくことに生きがいを見出すほかに生きる道はなかったのです。ザアカイの場合、お金が唯一の生きがいであり、慰めであったのです。
ユダヤ人はもはや誰も私のほうを見向きもしない。しかし、お金は私の思い通りに働いてくれる。私のために光り輝いてくれるという思いだけで、ザアカイは生きていたのです。ザアカイはそのようなものすごい自己分裂の中にいたといってよいでしょう。
ザアカイの内面的葛藤をよくよく理解することもなく、ユダヤ宗教共同体は、彼を罪人として追放しました。お宮では、まじめで信仰深い人たちが取税人を指さして「この取税人のような人間でないことを感謝します」と祈るようになりました。
教育ママが、自分の子供を教育するとき、ぐうたらでできそこないの自分の夫を指さして、「あなたはあんなパパのようにだけは、ならないでちょうだいね。ああいうふうにはなりたくないわねえ」というような具合、ちょうど同じような言われ方を、取税人たちがされていたのだ、と考えればいいと思います。
いや、そんな軽いものではなかったかもしれません。宗教的な群が自分たちの憎むべき相手に対抗する場合、神様の永遠の裁きを願い求めるのです。「あの男はわれわれの神様を捨てたのだ。どうか、あの男を滅ぼしたまえ」と祈られるのです。宗教的に断罪されるということは、究極的で最も根深い、のろわれ方であるのです。人間にとって生き地獄。ものすごい崖っぷちからつきおとされるかのごとく、激烈な絶望の中にたたきこまれるのです。
そのような中に、ザアカイはいたのです。彼にとって、何が慰めとなるというのでしょうか。何が楽しくて生きているというのでしょうか。話し相手も、仲間も、冗談言って笑う友人もいないところで、自分に運命的に与えられた仕事に埋没して、金でももうけている以外、どこに慰めがあるというのでしょうか。
そうです。誰が彼の金もうけを責めたてることができるというのでしょうか。ローマ帝国の支配下にあったのです。自由など何一つ許されない奴隷なのです。いくら正義とはなんだ、律法に絶対そむいてはならないのだ、と確信していることがあっても、それだけをただふりまわしても、現実を現実として生きる段になりますと、そんなことそっちのけで、精一杯、日ごとの糧とひとすくいの生きがいを、とにかく求めなければ生きていけないのです。あいつが悪い、あいつが間違っているという前に、自分たちのまわりの現実に対してもっと忠実になるべきでありますし、その間違っている相手のまわりにある現実を理解しなければならないのです。
ただ、ひとたびユダヤ人の立場に立って、ザアカイのほうを見てみますと、今まで言ってきたようにして、ザアカイのかたもちばかりをしていられなくなるのです。
ザアカイが苦しんでいる貧しいユダヤ人たちから高額の手数料をとって苦しめていたのは厳然たる事実です。いくらわたしたちが非行少年を見るとき、いくらその家庭環境が悪かったの、友達が悪かっだの、ついちょっとという気持ちは誰にでもあるのだからしかたないだとか、人道主義的に同情をよせてみても、彼の行った非行の事実はかくれてしまったりするものではないのと同じです。
私たち説教者がこの説教壇からまちがったことをいってしまって人をつまずかせてしまったときでも、いくらまだ先生は若いからとか、だれでもまちがいの一つや二つはあるもんだとか慰められたところで、その人がつまずいてしまったという事実は全く変わりなく残るというのと同じです。ザアカイは何としても弱い人を苦しめていたことには変わりがないことは認めざるを得ないのです。
では、やはりザアカイはイスラエル共同体から追い出され、憎まれてもしかたがなかったのでしょうか。もともとキリスト教信仰は人道主義とは縁もゆかりもないものなのです。正しいことを正しい、まちがっていることをまちがっているとはっきりということもできないような価値観はもっていません。いくら愛ということを説く宗教であっても、単なる同情心とかなれあいのようなものによって、黒を白としてしまうようなことはしないのです。ザアカイが罪を犯したことは明白なのです。
ではザアカイはいったいどのように裁かれるべきなのでしょうか。ザアカイとユダヤ人たちの前に、ついにイエス様がやってこられました。ひとたびイエス様の判断を仰ごうではありませんか。私たちがどう考えるかは、それからでもいいように思います。
ザアカイはイエス様がどんな人か見たいと思って、とにかくはせさんじました。あ、ザアカイのやつがきた、とユダヤ人たちは思ったにちがいありません。ザアカイは背が低かったとあります。それで集まった群衆にさえぎられたので、イエス様のことがよく見える木の上にのぼったのです。いちじく桑の木はぐねぐねまがっていて足をかけるところがあり、登りやすいのです。上からのぞきこむようにして、下を通るイエス様をながめるのです。
するとイエス様は、その木のちょうど真下にこられた時、真上をみあげられたのです。下からの視線と上からの視線がバチバチとあうのです。「ザアカイよ、急いで下りてきなさい。きょう、あなたの家に泊まることにしているから」。ザアカイは驚いたことでしょう。今まで誰も彼のほうをふりむいてくれた人はいませんでした。彼がいると気づくと、かえって目をそらして、フンとでも鼻であざけ笑われたことでしょう。しかし、イエス様は彼を見上げられたのです。偶然ではありません。あきらかに意志をもって、イエス様はザアカイをぎょうしされたのであります。
そして、ザアカイの家に泊まることにしてある、といわれるのです。人の家にとまって寝食を共にするということがどういう意味をもっているか、わたしたちはよく知っているのです。寝首をかかれるといいますが、全く無防備になるのです。首をかかれようが、頭をなぐられようが、いっさいを信頼し、相手に身をゆだねるのです。日本人がおじぎをするのと同じ意味をもっています。イエス様がザアカイに対してあたかもおじぎをするかのごとく、せまっているのです。しかも全く同時に、威厳をもって、力強くせまっておられるのであります。
そして、ザアカイは急いでおりてきて、よろこんでイエス様を迎え入れたのです。ザアカイは他の誰からも見向きもされないこと、そのことには何ら変わりのない中で、イエス様のほうから、友人として、客として入ってこられることによって、見出されるのであります。イエス様は、取税人を軽蔑する人々が群がっている中で、まさに自分たちこそ正しく、ザアカイこそまちがっていると信じて疑わない人々のまっただ中で、罪人であるザアカイと、彼1人をつかまえて、いのちの交流、心の真実なる交わりをはじめられたのであります。
罪人の赦しというのは、まさにこのような形でもって、わたしたちによろこびを与えるのです。これによってまたイエス様も、ユダヤ人たちから軽蔑され、つき従ってきた人々を落たんさせるにちがいないのです。類は友を呼ぶとかいわれて、イエス様もまた、ああ罪人とつきあうような同類かと、さげすまれるのです。イエス様が罪人の労苦と重荷を共に担おうとされるというのは、まさにこのような仕方でしか表わすことのできないものなのです。
今やザアカイは、イエス様のものであり、イエス様に追い求められ、イエス様に引きよせられ、守られているのであります。
そしてザアカイはかわっていくのです。日本には、三つ子のたましい百までとか、あの家にはゴクアクニンの血が流れているとか、人間とは変わることができない者なのだ、一度罪を犯したものは一生涯、また再び罪を犯すかもしれないという不信のまなざしのもとにおかれ、あいつは昔こうだったから、ということにいつまでもこだわられるのです。しかし聖書は人間というものが変わるものなのだ、神様によって赦しの言葉をうけると変わるのだと教えています。
私たちは、神様の教えの正しさをよく知っておりつつ、それに従うことのできない現実の中にいます。正義とは何か、愛とは内か、真理とは何かということを常日頃から学ぶ機会を与えられ、それをよく知っているのですが、現実の不条理の中で、今ここでやらなければならない仕事の中で、ひきょうといわれようと、さげすまれようと、それを見て見ぬふりをしつつ、策略と、小細工をくりかえしながら、商売をし、うまい世渡りをしてきました。人とつきあっている時でも、顔はにこやかにしてやっている時でも、心の中ではペロッとしたを出して、やりすごすことがままあると思うのです。そうでもしなければ、やっていけない、不条理な世界が、今ここにわたしたちの周りをとりかこんでいるように思えてならないのです。私たちもまたザアカイと同じなのです。ザアカイの罪は、私たちの罪でもあるのです。私たちはザアカイなのです。
イエス様はザアカイの罪を一方的に赦しました。ザアカイは、ただイエス様のところへ来た、たったそれだけのことをしたに過ぎないのです。保育所の紙しばいとか、いろいろな注解者が、ザアカイのイエス様のところにきた動機について、ザアカイは友達がいなくてさびしかったのだろうとか、ザアカイは取税人という罪人の仕事の中にむなしさを感じていたのだろうとか、いろいろな空想をこらしていますけれども、聖書にはただイエスがどんな人か見たいと思っていた、としか書かれていないのです。さびしかったとも空しかったとも書いていないのです。
彼はもしかすると、さびしかったのかもしれませんし、空しかったのかもしれません。けれどもまた、もしかすると、ただ単にイエス様の顔がどんな立派なものなのか、イエス様のことをただ見物しにきたのかもしれないのです。どんな立派な話をするのか聞いてやろうじゃないかと、物見ゆさんで来たかもしれないのです。
結局、とどのつまり、私がもしザアカイだったら、このときこういう状態だったにちがいないという想像にまかせるしかないのです。いや、もっというならば、イエス様のところに来た動機などどうでもいいことのように聖書が黙って語っているのだと思いたいのです。
ただイエス様のところに来た、その一事、それが大切なのです。ザアカイは、イエス様のもとにひざまずいて、あのマルタとマリヤの話のマリヤのごとく、弟子入りのスタイルをとって、おもむいていったわけでもないのです。無礼千万、上から見下(おろ)すように、見下(くだ)すといったら言いすぎでしょうか、そのような状態で、イエス様のところに近づいていったのでした。動機も問わない。方法も問わない。それにもかかわらず、イエス様は、ただ御自分のところに「きた」という罪人ザアカイを一方的に赦したのだ、ということを聖書は言わんとしているのではないでしょうか。
私たちは、このような人が教会に来るということが、どうも苦手なのではないでしょうか。動機が不純、教会にきたはいいけれど、あくびはするは、いねむりはするは、ついでにもともと前科者だというと、かんべんしてくれと言いたくなるのではないでしょうか。しかし、そのような人も、イエス様の下にくることによって、その全くもって一方的な赦しの御言葉をきき、うけ入れることによって、そのような人でさえ変えられていくのだということを、このザアカイ物語は語らんとしているのです。
私たちの教会に最初に訪れたときのことを思い出してみてください。動機は、と聞かれて、何か人にほこることができるようなものをもっている人がいるでしょうか。ただなんとなく、とか、親につれられて、友達にさそわれて、とかいうことで精一杯なのです。
しかし、きてみてはじめて、神様のことを知り、その愛を知り、それから自分自身の罪の深さを知り、そして、それをもまた赦し、受け入れてくださる神様の愛のかぎりなきあわれみと忍耐を信じることができるようになり、神様の約束を信じることができるようになったのでしょう。そして、その喜びの中で隣人にもまた、神様に教えられた愛のあり方によって愛することができるようになってきたのでしょう。
決して一朝一夕にわれわれの生活のあり方がかわるわけではありません。長い年月と苦労が必要でしょう。しかし、赦されたという事実は一瞬の出来事であり、われわれの生活のあり方が何ら変わらない時にも、罪のゆるしの事実もまた変わらずにあるのです。地球が自分自身では何ら光をはなつことはないにもかかわらず、太陽がいっぽうてきにこちらをてらすことによって、その光によって地球が光りはじめるのと同じです。
その何らよいことをしないままのザアカイを、先にイエス様がゆるされたことによって、ザアカイは、あふれる喜びのもとに、貧しい人にほどこしをし、今までしてきた搾取を4倍にしてかえそうという思いにみちびかれたのであります。
神様の豊かな愛を知って、自分自身の貧しさ、愚かさ、罪の深さを知り、もう、神様の赦しの御言葉をきかなければ、この先一歩も歩んでいくことができない。神様の赦しの御言葉、ただそれさえいただくことができれば、私は生きていくことができる。そのような群が、教会であります。
イエス様は十字架の上でいったい何を言われたのか、おもい出して欲しいのです。このルカによる福音書は、こう伝えているのです。「父よ、彼らをおゆるし下さい。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」。
御自分をまさに無実の罪で死刑台に、十字架にかけようとしている人々の罪をゆるして下さいと、イエス様は神様に向かって祈っておられたのです。私たちは、自分自身が何をしているのか、わからずにいるのです。何となく、世間の流れにまかせて、あるいは根拠のない自分の信念にまかせて、生きていって、神の御子を十字架にかけてしまうのです。だから主は、この祈りを祈りつつ、十字架にかけられて、罪の現実を見なさい、これが人間の罪だと、知らしめてくださっているのです。
ほんとに、どんな話でも十字架にくっつけるとか、キリスト教のことをあまりよく思わない人がいいます。それこそ、たしかに金太郎あめのように、いっつも十字架、十字架って言っているのが、キリスト教会です。二千年いいつづけてまいりました。宗教改革者マルティン・ルターの言葉を引用させていただきます。
「平安、平安と呼ぶ神父にわざわいあれ。
彼の下には十字架しかない。
十字架、十字架とつぶやく牧師に平安あれ。
彼はもはや十字架の下にいない。」
わたしたちは、人間の悲惨な現実をあばきだし、それを見せつけることとは全く無縁なのであります。そんなものは教会の目的でもなければ、手段でもありません。そんなものは私たちが日常の生活を真剣に生きようとしていたら、とっくの昔によく知っていることなのであります。自分の愚かさなど、よく知っているのであります。だから、赦しの言葉、ただそれだけが欲しいのです。
私たちは、この宍喰の町で礼拝を守っております。これから教会が成長していくのだという希望を与えられています。そのときに、わたしたちに与えられている一つの大きな課題は、ザアカイをわたしたちはうけ入れていかなければならないのだということなのであります。
今まで私たちのことを、ああキリストかと言って鼻で笑った人、過去において私たちを何かいやな目にあわせた人、感情的にイケスカない人、そのような人たちが何かのきっかけで教会に訪れて礼拝に出席しようという気になったとき、自分もまたザアカイであったのだ、ということを思いかえし、受け入れることができるか、ということ一点にかかっているのです。
できないのかもしれません。この聖書の箇所に、人々がザアカイをうけいれたかどうか何もかたられていません。この答えはみなさんに与えられた宿題なのかもしれません。
私の召命観というもの、伝道者にならせていただこうということの根本には、終始このことがあると思うのです。私のようなものでさえゆるされたのだ。罪がより深いものほど、赦されたときは多く赦されているのだと。その喜びを人にのべつたえようと。
(ここで原稿は終わっている。)