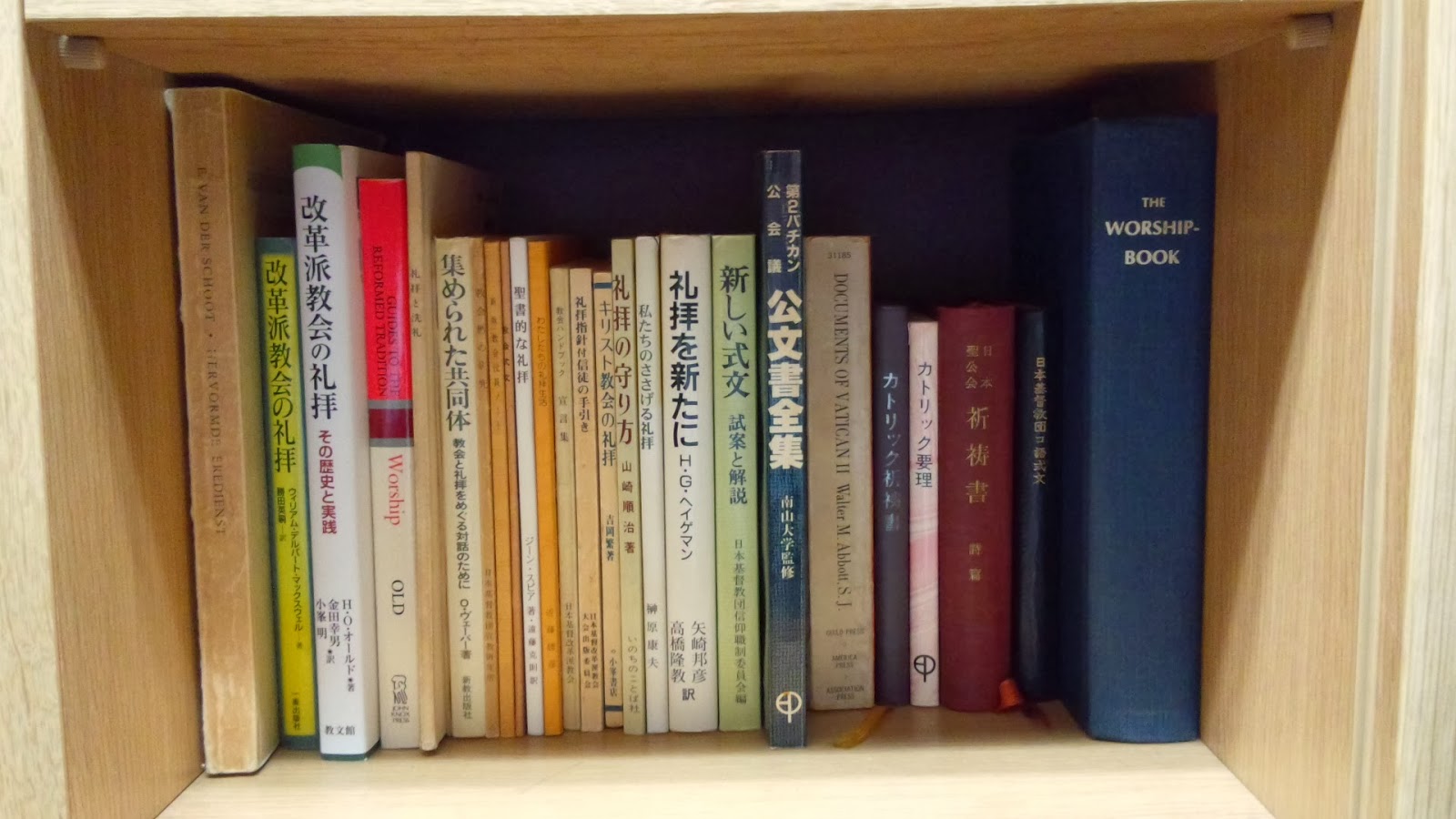リンク先の記事の前半3分の1くらいを訳してみました。
誤訳や読みこみすぎのところがあるかもしれませんが、あくまでもご参考までに、という程度でお許しください。
しかし、訳してみて分かったことは、サンダース氏の見方、そしてサンダース氏が紹介しているオランダの二人の神学者の見方には、同意できるところと、同意できないところがある、ということです。
ファン・ルーラーのことに限っては「あとだしじゃんけんだ」というようなことは言われたくない私ですが、彼らが指摘している点については、私もずいぶん前から気づいていました。しかし、私の見方は、彼らが言っていることよりも、あと一歩先のことです。彼らの指摘だけでは不十分だと、私には思えます。
私の見方は、3月24日(月)の「日本基督教学会関東支部会」(会場・東京女子大学)で申し上げます。それまでは、な・い・しょ、です。
フレッド・サンダース氏は、現在、米国バイオラ大学の組織神学の助教授です。
出典URLhttp://www.patheos.com/blogs/scriptorium/2009/07/christology-is-not-pneumatology-aa-van-ruler/------------------------------------------------------------------
「キリスト論は聖霊論ではない」(A. A. ファン・ルーラー)
フレッド・サンダース『組織神学国際雑誌』(International Journal of Systematic Theology)最新号でヘイスベルト・ファン・デン・ブリンク氏とシュテファン・ファン・エルプ氏が、20世紀のオランダの神学者による三位一体論的神学の再発見への貢献が欠如していたことを嘆いている。 論文のタイトルは「神が三位一体であることを無視しているのか――オランダ神学における三位一体論について」である。彼らは次のように述べている。「いくつかの重要な教理史的な研究書を除けば、20世紀オランダのプロテスタント神学において三位一体論とその影響について論じた本は一冊も出版されなかった」。この点はオランダのカトリック教会のほうがましだったと彼らは証言する。ファン・デン・ブリンク氏とファン・エルプ氏の報告によれば、オランダの有力なすべての神学者は三位一体論を無視し、放置した。あるいは自己目的に適応するようにねじ曲げ、大胆に再解釈した。あるいは完全に否定した。
二人の論者はアーノルト・アルベルト・ファン・ルーラー(Arnold Albert van Ruler [1908-1970])も取り上げている。しかし、彼らはファン・ルーラーを、影響力のあるオランダの神学者ではあるが、三位一体論自体に関心があったわけではなく、自己目的のために三位一体論を利用した神学者の一例として取り上げている。それで私は驚いた。これまで読んできたファン・ルーラーの本は三位一体論の諸命題で満ちていたからである。ファン・ルーラーがしばしば述べたことは、「キリスト論的神学だとか、聖霊論的神学だとか、そのようなものはあってはならない。キリスト論も聖霊論も神学全体の中の部分にすぎない。我々の目標は三位一体論的神学であるとしか言いようがない」ということであった。
しかし私は、ファン・デン・ブリンク氏とファン・エルプ氏の指摘を受けて、ファン・ルーラーの文章を自分で確かめた。それで分かったことは、ファン・ルーラーが実際に関心を持っていたのは神学の包括性(comprehensiveness)の問題であったということである。彼は三位一体論のカテゴリーを、神学の包括性を獲得する方法であると考えていたのだ。彼が好んで用いた言葉は「○○だけではなく(not only)、△△もまた(but also)」である。彼が願ったことは、なるべく広く網を張ることであり、より多くの知識や情報を獲得することだったからである。二人の論者は、ファン・ルーラーの方法を「三位一体論的拡張」(trinitarian spreading)の技法であるとみなす。そして、この点こそが「ファン・ルーラーは自己目的のために三位一体論を利用した神学者である」という彼らの指摘の根拠になっている。「開放的な多様性において、ありとあらゆることが未解決のままであり続けること」を確保することがファン・ルーラー自身の計画でもあったということが、「三位一体論的神学の必要性」という彼の論文を読むと分かる。多くの現代的な神学者がいまだにそうであるように、ファン・ルーラーは、多様性(三位!)についてのきわめて抽象的な概念が同時に究極的に一致すること(一体!)に興奮を覚えた人である(ちなみに私は、現代神学者たちの三位一体論の捉え方は間違っていると考えている)。そして彼は、三位一体の神存在に秘められた「区別性と関係性」という概念を発見した。その線に沿ってどこまでも進んでいけばよい。そうすれば、「三位一体論的発想法」(trinitarian thinking)という大いなる関心事に辿り着くだろう。しかしそれは、三位一体論そのものについて考えることではないのである。
ファン・ルーラーは依然として、読むと非常に刺激を受ける本を書いた神学者である。彼の株価は今後数十年で上昇するだろうと私は予想する。彼の著作集を出版し続ける愛読者がいる。英語や日本語に翻訳されている。あなたは二色の蛍光ペンを用いて彼の本を読むことができる。そのペンの一本は、彼の全作品に見つかる燦然と輝く黄金の命題をチェックするために用いればよい。もう一本は、これもまた彼の本のすべてのページの至るところに散りばめられた、ひどく間違っていて危険極まりない言葉をチェックするために用いるべきだ。ファン・ルーラーの三位一体論についての発言が三位一体論そのものとは異なる関心によって動機づけられていたことを指摘してくださったファン・デン・ブリンク氏とファン・エルプ氏に、感謝を申し上げたい。